こんにちは!ケントです!
今回は1次式の除法のやり方について解説します!
これまでの内容に不安が残る子は
以下のリンクから復習してみてください!
✅ なんで数学で文字を使うの?
→ 文字と式とは?
✅ 文字の書き方のルールは?
→ 文字式の5つのルール
1次式の除法のやり方 ポイント①
まず、除法とは割り算のことでした。
基本的な割り算に不安が残る子は
下のリンクから復習してみてください!
乗法・除法
1次式の除法のポイントは2つです。
ポイント① 係数をその数で割る
具体的に、12\(x\)÷3を考えてみましょう。
12\(x\)の係数は12なので、係数12を3で割ります。
12÷3=4ですね!
結果は、12÷3×\(x\)=4\(x\)となります。
係数は文字の前についている数のことでしたね。
次に、(-6\(x\))÷2を考えてみましょう。
-6\(x\)の係数は-6なので、係数-6を2で割ります。
-6÷2=-3ですね!
結果は、(-6)÷2×\(x\)=-3\(x\)となります。
1次式の除法のやり方 ポイント②
ポイント② 係数に割る数の逆数をかける
小学校の割り算でも次のような計算をしたことがありますよね?
3÷\(\frac{3}{2}\)
これは、\(\frac{3}{2}\)の逆数すなわち、
\(\frac{2}{3}\)をかけてあげれば計算ができました。
「Aで割る」=「逆数の\(\frac{1}{A}\)をかける」
というルールがありましたね!
分数で割る計算が出てきたときには
逆数をかけてあげることで計算ができるのです。
具体的に、8\(x\)÷\(\frac{2}{3}\)を計算してみます。
\(\frac{2}{3}\)で割ることは
\(\frac{3}{2}\)をかけることと同じなので
8\(x\)÷\(\frac{2}{3}\)
=8\(x\)×\(\frac{3}{2}\)
=12\(x\)
このような計算になります。
ポイント①もポイント②も本質は同じ計算です!
項が2つの除法
\(\frac{6x+12}{3}\)はどのように計算すれば良いでしょうか?
これは、\(6x\)と\(12\)のどちらも\(3\)で割る必要があります。
\(6x\)÷\(3\)=\(2x\)
\(12\)÷\(3\)=\(4\)なので
答えは、\(2x+6\)となります!
項が2つあるときの除法は
それぞれの項の係数やその数を割ってあげればOKです!
確認問題をやってみよう!
1次式の除法のやり方が分かったところで
ここで確認問題をやってみましょう!
【確認問題】次の①〜③の計算をしなさい。
①4\(x\)÷2 ②(-8\(z\))÷4 ③3\(y\)÷\(\frac{3}{2}\)
まとめ
1次式の除法のやり方をまとめました!
忘れないようにノートにメモしておきましょう!
【1次式の除法のやり方のまとめ】
①係数を割る
②係数に割る数の逆数をかける
→割る数が分数のとき
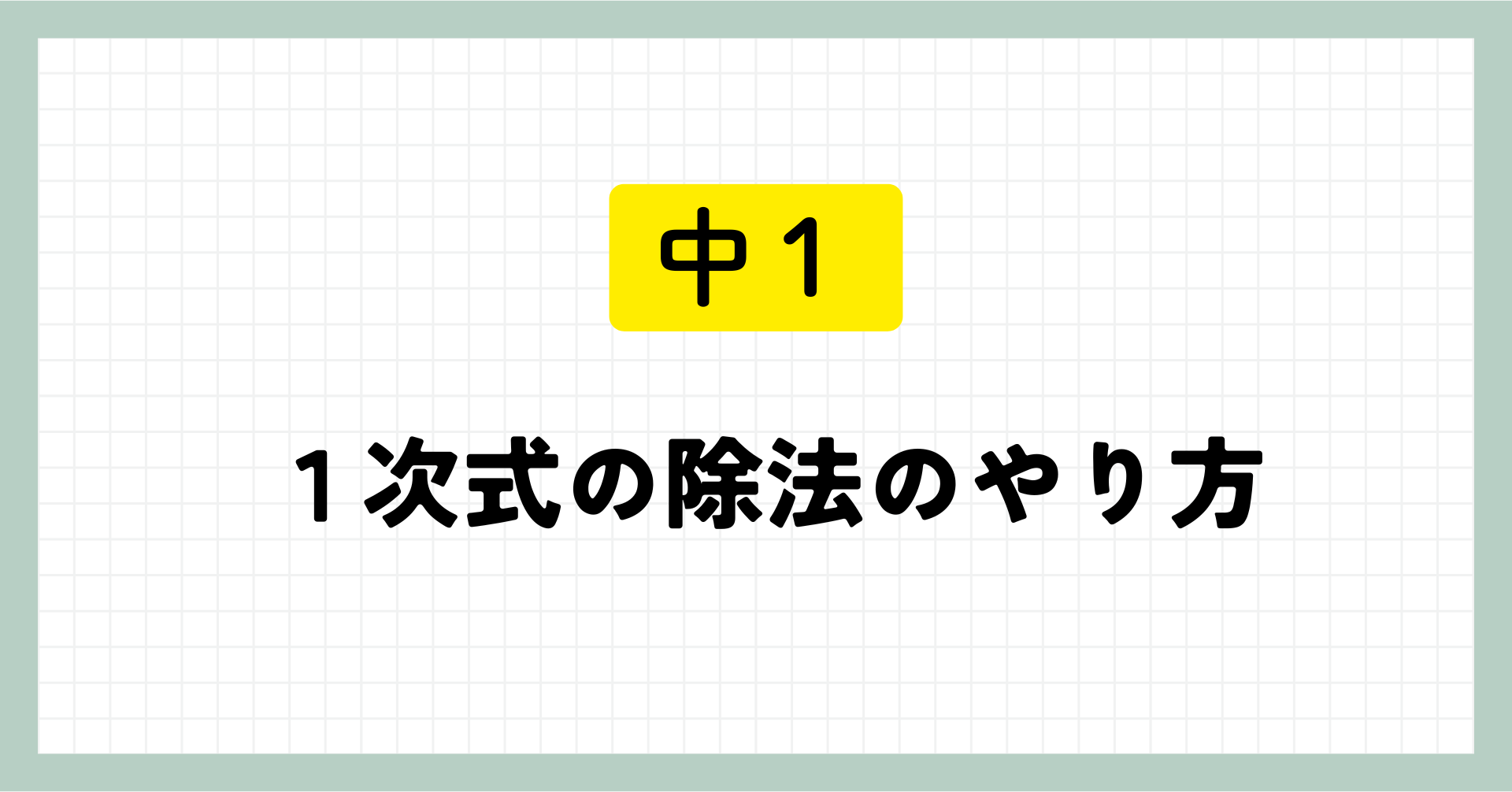
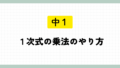

コメント